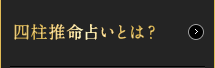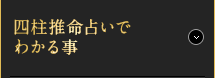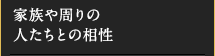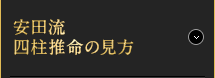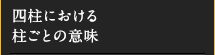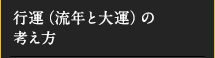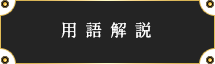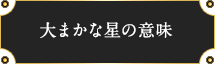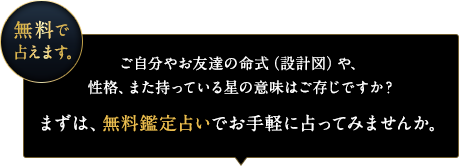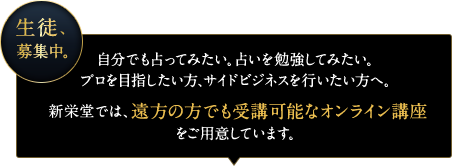「陰陽五行」とは、中国の春秋戦国時代ごろに発生した陰陽思想と、五行思想が結び付いて生れた思想のことをいい、東洋哲学(特に中国)における「宇宙の根本原理」であり、同時にそれが、中国に起源する易学や推命学などの占術、或いは漢方医学や鍼灸等の根本原理ともなっています。
「陰陽五行の理法」とは全ての事象は、それだけが単独で存在するのではなく、「陰」と「陽」という相反する形(例えば明暗、天地、男女、善悪、吉凶など)で存在し、それぞれが相対的な関係を持って存在するとしています。さらに万物は「木・火・土・金・水」という五つの要素により成り立ち、その五行にも各々「陰と陽」があり、それらの五行の相生と相尅の相互関係によって、様々な作用と現象が現れるとしています。
| 原因 | 太極 | 陽(+):主体 | 陰(-):対象 |
|---|---|---|---|
| 結 果 |
鉱物 | 陽イオン | 陰イオン |
| 植物 | オシベ | メシベ | |
| 動物 | 雄 | 雌 | |
| 人間 | 男 | 女 |
- ※太極(原因)の世界が陽と陰で出来ているために、結果(現実)の世界も陽と陰で出来ている。
また、陽と陰の相互関係から様々な力が発生する(存在・生育・発展等)。
五行思想(ごぎょうしそう)とは、古代中国に端を発する自然哲学の思想で、万物は、木・火・土・金・水の5種類の元素からなるという説である。また、5種類の元素は『互いに影響を与え合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する』という考えが根底に存在する。
五行(木火土金水)にも陰陽があるが、古代中国ではそれを下の表の様に干支であらわした。
天干のことを「天の五行」、地支のことを「地の五行」とも呼び、それぞれ十干・十二支で表現した。
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天の十干 (天干) 天=無形 (心) |
陽(+) | 甲 (きのえ) |
丙 (ひのえ) |
戊 (つちのえ) |
庚 (かのえ) |
壬 (みずのえ) |
| 陰(-) | 乙 (きのと) |
丁 (ひのと) |
己 (つちのと) |
辛 (かのと) |
癸 (みずのと) |
|
| 地の十二支 (地支) 地=有形 (身体) |
陽(+) | 寅 (とら) |
午 (うま) |
辰・戌 (たつ・いぬ) |
申 (さる) |
子 (ね) |
| 陰(-) | 卯 (う) |
巳 (み) |
丑・未 (うし・ひつじ) |
酉 (とり) |
亥 (い) |
十干とは、甲(きのえ・コウ)、乙(きのと・オツ)、丙(ひのえ・ヘイ)、丁(ひのと・テイ)、戊(つちのえ・ボ)、己(つちのと・キ)、庚(かのえ・コウ)、辛(かのと・シン)、壬(みずのえ・ジン)、癸(みずのと・キ)の十種をいい、五行を兄(え)…陽干と、弟(と)…陰干に分けたものに当てはめたものです。
- 1. 甲(きのえ/コウ)
陽の木で、大木を意味します。万物が種の甲を破って、上へ伸びようとする気概を持つ性質があります。
人の中心に立つ人が多く、人情的な干です。男性のリーダーが多く、暖か味があります。 - 2. 乙(きのと/オツ)
陰の木で草花枝葉にたとえられます。
乙女などと言われるように、女性的な干ですので、女性にはよい星です。
男性でも、当たりは柔らかくても技術や特殊な才能を発揮している人も多くいます。
優しくひ弱そうに見えますが、辛抱強く、目的に向かって進む性質があります。
意外とプロレス・相撲・柔道などの格闘技の有名選手に多くいました。 - 3. 丙(ひのえ/ヘイ)
陽の火で、燃え盛る火、又は太陽を意味します。
派手で、明るく、カラッとした性格の人が多い星で、人の中心的存在になることも多く、天干の中では一番財運のある干です。 - 4. 丁(ひのと/テイ)
陰の火で、灯火・人工の火にたとえられる。
この日干の人は緻密な神経をもった人が多く、秘書や参謀などで非常に頭の切れる人によくある星です。 - 5. 戊(つちのえ/ボ)
陽の土で、山や、堤防の土にもたとえられます。
この干は丙のような派手さはありませんが、山は木を養うところから、人を面倒見たりする包容力のある人が多い星です。
地味ですが大きな組織の責任者にも多い星です。 - 6. 己(つちのと/キ)
陰の土で、田園の土にたとえられます。
戊に比べて小さい領域の土です。
あまり組織の責任者には向きませんが、小さい領域の中で小人数の技術集団とかが向いています。
派手さはありませんが大衆的、人情的な星です。 - 7. 庚(かのえ/コウ)
陽の金で、鉱石・鉱脈などにたとえられます。
石の「硬さ」から、「頑固さ」という面がありますが、四柱組織如何によって、性格は柔らかくても印象として難いイメージを持たれる人もいます。
また、感受性が強く、感覚的な星でもあり、天干の中では一番宗教性があるとも言われています。 - 8. 辛(かのと/シン)
陰の金で、砂金や珠玉・貴金属にたとえられます。
この日干の女性は宝飾関係が似合う方が多いようです。
辛抱の「辛」の字でもありますので、辛抱強く粘り強く人生を歩んでいる人も多くあります。
少々神経質な面もあります。 - 9. 壬(みずのえ/ジン)
陽の水で、大河や大海にたとえられ、流れてとどまらない強さをもちます。
何かと水には縁のある星で、水商売や夜のお仕事の人も多い星です。
クールな所がありながら、行動力と迫力をもっている人も多い星です。 - 10. 癸(みずのと/キ)
陰の水で、雨水・雨露・霧にたとえられます。万物を育てる根源となり、優しく人に奉仕します。
男性は陽干の丙などに比べて、一寸見は地味で風采の上がらない人が多いのですが、この星は教育関係など頭脳労働的な働きをする星です。
また壬同様に何かと水と縁のある星です。
十二支について。(暦の事典から)
月の十二支(十二辰)は、草木の発生・繁茂・成熟・伏蔵の過程、つまり陰陽の消長する順序を十二支の段階に分けて名付けたものである。月の十二支が十二か月の各月の特性を示したものであるように、もともと時の十二支は一日における十二刻特 性を示したものであり、方位の十二支は十二方位の特性を示したものであった。
- 1. 子
子は滋(し)で、種を水に浸すことで柔らかくなり、万物が育ち始める意味があり、陽支の水となります。
【日支にある場合】
知性的だが、冷たく客観的に物事を見つめ、細かいことに気がつく。
変化を求め、器用で小才がきき、倹約家で、利害に敏感なところがある。 - 2. 丑
丑(ちゅう)は紐(ちゅう)で、むすぶの意味があり、湿土を種にかけて冬を越し、春を待つ姿です。
【日支にある場合】
保守的で信用を重んじる。財運はあるが、あまり大金持ちになれる方ではない。
正直、堅実、けち。
人懐っこく涙脆い。弱気と強気が共存する。 - 3. 寅
陽支の木であり、寅(いん)は演(えん)で、春になって始めて、地上に新芽を出す様を表しています。
【日支にある場合】
正直で誠実。積極的な行動をとる。
陽気で明るく人を楽しませる。仁義や友情に厚い。独立型。
財に対する執着心は淡白。権威と頭領運もある。 - 4. 卯
陰支の木で、卯(ぼう)は茂(ぼう)茆(ぼう)で、春たけなわとなり万物が茂ることを表します。
【日支にある場合】
綿密なる思想と豊かな情緒を持っている。発明発見など思考的な仕事が良い。
自己主張が強い。放任の傾向に注意。美的感覚に優れている。
- 5. 辰
陽支の土で湿土を表しますが、辰(しん)は震(しん)で、大地を揺さぶるほど根を張ることを示します。
【日支にある場合】
意志強固、不屈の頑張りがきくのでどの道でも力を発揮する。
感情の起伏が大きい。事業家・独立家で一生波風が多く慎重なら吉。芸術的才能あり。 - 6. 巳
陰支の火で、巳(し)は已(い)で、已(すで)に万物が盛りを極めて、これから実を結ぶ時期に移ることの意味があります。
【日支にある場合】
勇気、行動力を意味する。変わった商売を選ぶ。
思い込むと執拗なところがある。
外見は冷たい感じでも内心は温かい。礼儀を大切にする。 - 7. 午
陽支の火で、午(ご)は忤(さからう)で、陰気が下から上がり、陽気と相逆らい交わることをいいます。
【日支にある場合】
明朗で直観力が鋭く直情径行型、負けず嫌い。じっとしているのが苦手。
機敏と人間的な親切さを主体とする職業が良い。色情と口舌にトラブルあり。 - 8. 未
陰支の土で、未(み)は味(み)で、万物が出来上がって美味しく味わう意味です。
【日支にある場合】
知性的な一面がある。物事に柔軟で丁寧で遠慮深く取り越し苦労性。
金銭的にちゃっかりしている。人を巧みに利用するのが上手だが人には好かれる。 - 9. 申
陽支の金で、申(しん)は身(しん)で、万物の身体ができる、伸(しん)の字を当てはめています。
【日支にある場合】
口八丁手八丁、才気もあり話好きで社交上手。
魅力があり愛嬌を要する仕事に就くとよい。
完全性を追求する気難しさもある。先取りの気性あり。 - 10. 酉
陰支の金で、酉(ゆう)は醸(じょう:かもす)で、酒器、すなわち秋の収穫した作物を加工して蓄える意味があります。
【日支にある場合】
敏感、正確なので、知的な方面の仕事をするとよい。智に溺れやすい傾向もある。孤独を愛し、気難しいところもあります。 - 11. 戌
陽支の土で、戌(じゅつ)はもたっとした乾土で、蓄える作物を土中に埋めて、それを戌(まもる)役目をします。
【日支にある場合】
たえざる情熱をもって精進する。忍耐強く義理人情に厚い。
怒気も強い。 - 12. 亥
陰支の水で、亥(がい)は核(かく)で、万物が次代の種になることを示しています。
【日支にある場合】
沈着、熟練、冷静、物事に対して、直進して解決するので、独断になりやすい。
世話好きで、涙もろく、派手さはないが、誠実さがとりえです。
さらに詳しい内容を知りたい方はこちら:
- ・十干と十二支詳しくはこちら
五行には、大きく分けて、「相生」と「相尅」という2つの作用(相互関係)があります。簡単に言えば「相生」とは、ある五行がある五行を強める関係、「相尅」とは、ある五行が、ある五行を弱める関係をいいます。そして、それらが五行(木火土金水)の中でなされています。
自然現象に譬えて説明しますと、「相生」とは、「木は燃えて火を生じ、火は土(灰)を生じ、土中からは金(鉱石等)が生じ、金(岩)から水が生じ、水は木を生じ育成する」という原理です。そして、「相尅」では、「木は根を張って土を尅し、土は堤防となって水を防ぎ、水は火を尅して消し、火は金を尅して溶かす」作用のことです。五行図で言えば、「相生」は隣同士の関係であり、「相尅」は一つおいた次の五行との関係となっています。 概ね、「相生」は吉作用、「相尅」は凶作用と捉えることが出来ますが、そこは四柱推命の奥深いところで、「相生」必ずしも吉ならず、「相尅」必ずしも凶ならずとなります。却って凶星が生じられること(相生)によって凶作用を増すこともあり、逆に凶星が尅(コントロール)されることによって、凶星の凶作用が抑制されることがあるからです。

「相生」とは、互に「生じあう」関係のことで、下記の様な関係となっています。
- 1 木生火…「木は火を生じる」
木は、燃えて火を発生させます。これは火の立場からすれば、火が燃えるのを木が助けてくれることを意味しています{易理では木は「巽」で風(空気)を意味し、風は火の勢いを強める}。また、木の立場から言えば、木の潜在的なエネルギー(才能)が火となって発現(自己表現、煮炊きや明り)されることを意味しています。しかし、木自体は消耗します。(この場合、木が母親なら、火は子供の様な関係です。木から火が生じるわけで、母親は子供に母乳を与えればエネルギーを消耗します、しかし子供は育ちます。) - 2 火生土…「火は土を生じる」
火は燃え尽きて灰となり、その灰が何世紀も経てば土と化します。また、陶磁器などでは火は粘土を焼き固めて強固な土(器)としてくれます(瓦やレンガ等)。また、太陽の熱を地面が吸収するという事象にも譬えられ、適度な火(太陽)と土(畑)の関係は良質な作物等を生み出します。しかし、過度の火と土の関係では、日照りで田畑が乾燥して、作物を育てることが出来ない土となります。土の用途と性質によって「火生土」も良く働いたり悪く働いたりします。(この場合にも火が母親なら土は子供の様な関係です。エネルギーを与える方はやや消耗し、貰う方は太ります。) - 3 土生金…「土は金を生じる」
大地の中から金(金銀・鉱石・宝石等)などが採掘される事象に譬えることが出来る関係です。良き山(鉱山)は宝の山となって、宝である金を産出することができます。しかし、土が多過ぎる場合には、多過ぎる土に金が埋もれてしまい(埋金)、世に出ることが出来なくなる場合もあります。この「土生金」の相生の関係は、通常は吉作用ですが、前述の通り、バランスが崩れると凶作用になることもあります。 - 4 金生水…「金は水を生じる」
土壌の中の岩間(金)から水が生じることに譬えられます。また、寒い冬などは車の鉄板やガラスに水滴が付く場合もあります。金の側から見ると「金生水」は金の潜在能力を引き出す作用があり、水の側から見ると、金は水を生み出してくれる「水源」となります。 - 5 水生木…「水は木を生じる」
水が木(植物)を育成する作用に譬えられます。しかし、水が多過ぎると木が腐ってしまったり、また、流木となって流されてしまうこともあります。適度の水であってこそ、木(植物)を育成する吉作用となります(実際の鑑定では適度な水と熱ですね)。
「相尅」とは、互に「尅し合う」関係のことで、下記の様な関係となります。
- 1 木尅土…「木は土を尅す」
木は土中に根を張ることによって、土を押しのけ土の養分を吸収します。木(植物)は過度に繁茂し過ぎると、土は痩せてしまいます。逆に土が強過ぎて硬くなっても、木は根を張ることが出来ず、木も反尅作用を受けて育ちません。 - 2 土尅水…「土は水を尅す」
土は堤防となって、水が氾濫するのを防ぐ作用をします。しかし、土が強過ぎたり悪い土の場合は、水は濁ってしまうことになります。また、逆に水の勢いが強過ぎると、土も反尅作用を受けて堤防決壊となり、水が氾濫してしまうこともあります。適度なバランスが重要です。 - 3 水尅火…「水は火を尅す」
水は火を尅して消す作用をします。適度な水は火の凶勢を抑えてくれ、水も火の反尅作用によって暖められることもありますが、強過ぎる水は完全に火を消してしまって、火の効用までも無くしてしまうこともあります。また、強過ぎる火に水を注ぐと却って水蒸気爆発の様になり、火を消すどころか、暴発させてしまうこともあります(火と水の相尅関係は注意が必要です)。 - 4 火尅金…「火は金を尅す」
火は金を尅して金属を溶かし変形させる作用をします。金が善用されるには適当な火で鍛錬される事が大切です。金が器を成し名刀となる為には、火の勢いが金の力量に対して適度である必要があります。火の勢いが強過ぎれば鋼も完全に溶けてしまい、器(名刀)を成すことが出来ません。
鉱石も溶鉱炉で溶かさねば、役立つ鉄にはなりません。 - 5 金尅木…「金は木を尅す」
金は斧や鋸となって木を尅し伐採します。木(甲)は金によって伐採されて、切り刻まれ加工されることによって、人の役に立つ家や家具等の有用な材となることができます。逆に木が堅過ぎれば、木の反尅作用を受けて、金(斧や鋸)も刃こぼれしてしまうことがあります。また植木等(乙)は適度に剪定されると立派な樹木になりますが、切り過ぎると枯れてしまいます。バランスですね…。
- 1. 確りした「木」の気があると、その性質は直にして仁心(じんしん)を抱くと言われます。人に優しさや暖かさを与える面があります。
- 2. 確りした「火」の気があると、明るく礼節を尊ぶと言われます。しかし、カッときやすく、派手さも出る場合があります。原色が似合う人が多い様です。
- 3. 確りした「土」の気があると、寛大で和と信を重んじると言われています。人を育み面倒を見るという意味になります。
- 4. 確りした「金」の気があると、やや神経質な面はありますが、剛毅果断で義を重んじると言われています。
- 5. 確りした「水」の気があると、沈着冷静で智恵があると言われます。悪く言えば、人に冷たさを与えてしまう場合もあります。
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作用 | 曲 直 | 炎 上 | 稼穡 | 従 革 | 潤 下 |
| 五時 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |
| 五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |
| 陰陽 | 少 陽 | 太 陽 | − | 少 陰 | 太 陰 |
| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |
| 五声 | 角 | 徴 | 宮 | 商 | 羽 |
| 五能 | 生 | 長 | 化 | 収 | 蔵 |
| 五常 | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 |
| 五臓 | 肝臓 | 心臓 | 脾臓 | 肺臓 | 腎臓 |
| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |
| 五根 | 目 | 舌 | 唇 | 鼻 | 耳 |
| 五主 | 筋・爪 | 血脈 | 唇・肌肉 | 皮・毛 | 骨・髪 |
| 五志 | 怒 | 喜・笑 | 思・憂 | 悲 | 恐・驚 |
| 五情 | 怒 | 楽 | 欲 | 喜 | 哀 |
| 五感 | 視 | 聴 | 臭 | 味 | 触 |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 |
| 五禁 | 辛 | 鹹(シオカライ) | 酸 | 苦 | 甘 |
| 五穀 | 麦 | 黍(キビ) | 稗(ヒエ) | 稲 | 豆 |
| 五畜 | 鶏 | 羊 | 牛 | 馬 | 豚 |
| 五果 | 李(スモモ) | 杏(アンズ) | 棗(ナツメ) | 桃 | 栗 |
| 十干 | 甲・乙 | 丙・丁 | 戊・己 | 庚・辛 | 壬・癸 |
| 十二支 | 寅・卯 | 巳・午 | 辰未戌丑 | 申・酉 | 亥・子 |
| 元素 | 有機物 | 熱物質 | 土壌 | 金属類 | 液体物 |
| 四神 | 青龍 | 朱雀 | − | 白虎 | 玄武 |
| 八卦 | 震・巽 | 離 | 坤・艮 | 乾・兌 | 坎 |
さらに詳しい内容を知りたい方はこちら:
- ・五行詳しくはこちら